地方の交通インフラとして重要な役割を果たしてきた富山地方鉄道が、深刻な経営危機に直面しています。
2023年度には約7億円の赤字を計上し、幹部が「このままでは路線の縮小や廃止も選択肢だ」と警鐘を鳴らしました。
当記事では、地鉄の現状や打開策、地域交通の未来について深掘りします。
富山地方鉄道の経営状況と路線縮小の現実
富山地方鉄道(地鉄)は、2023年度の鉄道事業において約7億円の赤字を抱え、厳しい経営が続いています。
特に利用者の減少が大きな打撃となっており、これまでのような路線維持が困難になってきているのが現状です。
専務取締役・新庄一洋氏は、連合富山が開催した研修会にて、「社員の待遇を低下させてまで鉄道線を維持している」と述べ、企業努力にも限界があることを訴えました。
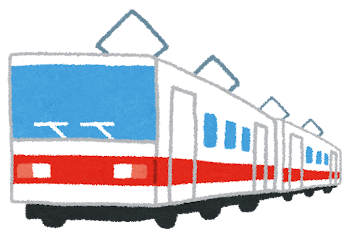
打開策としての運賃改定と大幅な減便の効果とは?
2025年4月、地鉄は運賃の値上げと大幅な減便という抜本的な見直しを行いました。
しかしながら、この対策による経営改善効果は限定的で、根本的な収支改善には至っていません。
また、利用者からは、
・「運賃が高くなって利用しにくくなった」
・「本数が減って通勤通学に不便」
といった声も上がっており、サービスの質と収益性のバランスが大きな課題となっています。
地鉄専務が語る今後の展望と不採算区間の廃止の可能性
新庄専務は、「これから先の協議では、一部区間の廃止も選択肢となる」と明言しています。
長年地域に根差してきた路線の縮小については、企業としての誇りと使命感から「判断は揺れ動く」としつつも、現実的な選択肢として廃止を視野に入れていることがわかります。
加えて、県や沿線自治体に対しては、「早急な支援と参画」を強く求めており、行政との連携が路線存続の鍵を握っていると言えるでしょう。
地域鉄道が果たす役割と公共交通としての重要性
富山地方鉄道は、通勤・通学・通院など、日常生活に欠かせない移動手段として地域に根付いてきました。
特に高齢者や学生にとっては代替手段が少なく、公共交通としての役割は極めて重要です。
このような鉄道が廃止されれば、地域の人口流出や経済活動の低下にもつながる恐れがあり、「採算性」だけで判断できない側面が存在します。
ネット上での反応と声
ネット上では、
・「これまで地元の足として頑張ってきたのに残念」
・「赤字でも守ってほしい」
・「行政がもっと支援すべき」
といった地元住民からの支援を望む声が多数上がっています。
一方で、
・「利用者が減っているのは事実」
・「経営が続かないなら仕方ない」
といった冷静な意見や現実的な視点も見られ、地域交通の在り方について多様な議論が起こっています。

まとめ:富山地方鉄道の未来を守るために必要な視点
富山地方鉄道の経営危機は、単なる一企業の問題にとどまらず、地域交通の在り方そのものが問われている状況です。
地鉄がこれまで守ってきた地域の「足」を維持するためには、企業努力に加え、自治体・住民・国による連携と支援が不可欠です。
「採算が取れないから廃止」ではなく、「どうすれば持続可能にできるか」を共に考えることが、地域の未来を守る一歩になるはずです。
当記事は以上となります。













コメント