近年、駅や商業施設、さらには公共トイレなどでの盗撮被害が後を絶ちません。
特に2024年12月、富山県で起きた実際の盗撮事件は、多くの人々に衝撃を与えました。
当記事では、その実例をもとに、被害者の証言や法制度の課題、示談ビジネスの問題点、そして今すぐできる盗撮防止策などについて掘り下げます。
被害に遭わないために、また誰かを守るために、ぜひ最後までお読みください。
実際に起きた盗撮事件とは?被害者の証言あり
2024年12月4日、富山駅前の雑居ビル内の男女共用トイレにて、20代の女性が盗撮被害に遭いました。
女性がトイレに入ると、ドアの上部にあるわずか5センチの隙間からスマートフォンが差し込まれていることに気づき、恐怖で声が出なくなったと証言しています。
その後、加害者の男性は自首し、「富山県迷惑行為等防止条例違反」で書類送検されましたが、女性は「画像の流出が何よりも怖かった」と語っています。
被害者が感じる恐怖と不安は、事件発覚後も長く続くのが現実です。
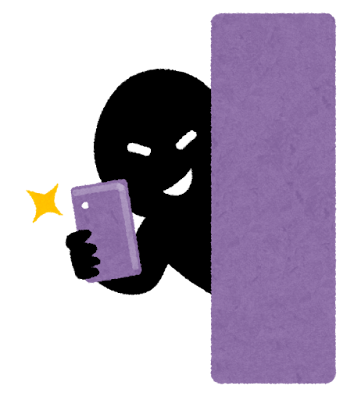
なぜ盗撮は減らないのか?制度と社会の落とし穴
2023年に施行された性的姿態撮影処罰法では、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という厳しい刑罰が設けられました。
しかし現実には、盗撮被害は減少していません。
富山県では2024年、114件の違反が確認され、前年より48件も増加しています。
問題の一因は、「証拠主義の壁」にあります。
加害者が罪を認めても、証拠が不十分だと起訴が難しいケースが多く、被害者は泣き寝入りを強いられがちです。
また、被害者が証言を変える可能性を懸念し、示談を勧めるケースもあり、司法の限界が露呈しています。

泣き寝入りを誘発する“示談ビジネス”の闇
盗撮事件の被害者支援を行うPAPS(ポルノ被害と性暴力を考える会)によると、弁護士が加害者側の相談に応じ、示談成立で報酬を得る“ビジネスモデル”が存在しているといいます。
これは、被害者が本来受けるべき法的救済の道を狭めてしまう危険な構造です。
「加害者が家族に申し訳ないと法廷で謝罪しても、被害者には無関心」というケースもあり、本質的な反省が伴っていないまま、執行猶予や罰金で終わる現状が問題視されています。
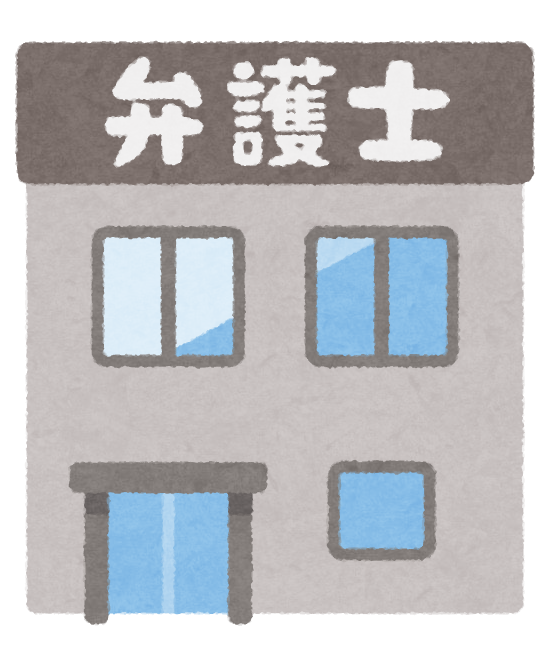
盗撮を防ぐためにできること:警戒の姿勢が抑止力に
富山県警の三島大輔氏は、「犯人は見られていると犯行を躊躇する傾向がある」と指摘しています。
したがって、後ろを振り向く、周囲に注意を向けるといった“警戒姿勢”が有効な抑止策となります。
また、公共トイレではなるべく個室の構造を確認し、カメラを設置できる隙間がないかをチェックすることも大切です。
日頃の小さな意識が、大きな被害を防ぐ鍵となります。

私たちにできる支援と社会的理解:盗撮被害者を孤立させないために
盗撮などの性被害は、被害者が声を上げにくいという特徴があります。
そのため、社会全体が「他人事ではない」という意識を持つことが重要です。
支援団体への寄付、SNSでの情報拡散、正しい法知識の共有など、私たちにできることは多くあります。
まずは盗撮が実際に起きている現実を知り、周囲に共有することが第一歩です。

ネット上での反応と声:被害者に共感と怒りの声広がる
この事件が報道されると、ネット上では下記のような反応が見られました。
・「まさかこんなことが公共トイレで…怖すぎる」
・「加害者が軽い刑罰で終わるのは納得いかない」
・「自分の娘や恋人が被害に遭ったらと思うとゾッとする」
・「もっと被害者に寄り添った制度を」
これらの声は、盗撮が社会全体の課題であることを示す強いメッセージとなっています。

まとめ:盗撮は“日常の落とし穴” 私たちは無関心でいられるか?
盗撮被害は、法改正だけでは根絶できません。
制度の不備、社会的無関心、そして“示談ビジネス”という構造的課題が重なり、被害者が泣き寝入りする構図が続いています。
しかし、この記事を読んだ人が「知ること」「共有すること」「警戒すること」で、被害の抑止や被害者の支援に貢献できます。
ご自身、そして大切な人を守るために——今日からできる行動を始めてみませんか?
当記事は以上となります。










コメント